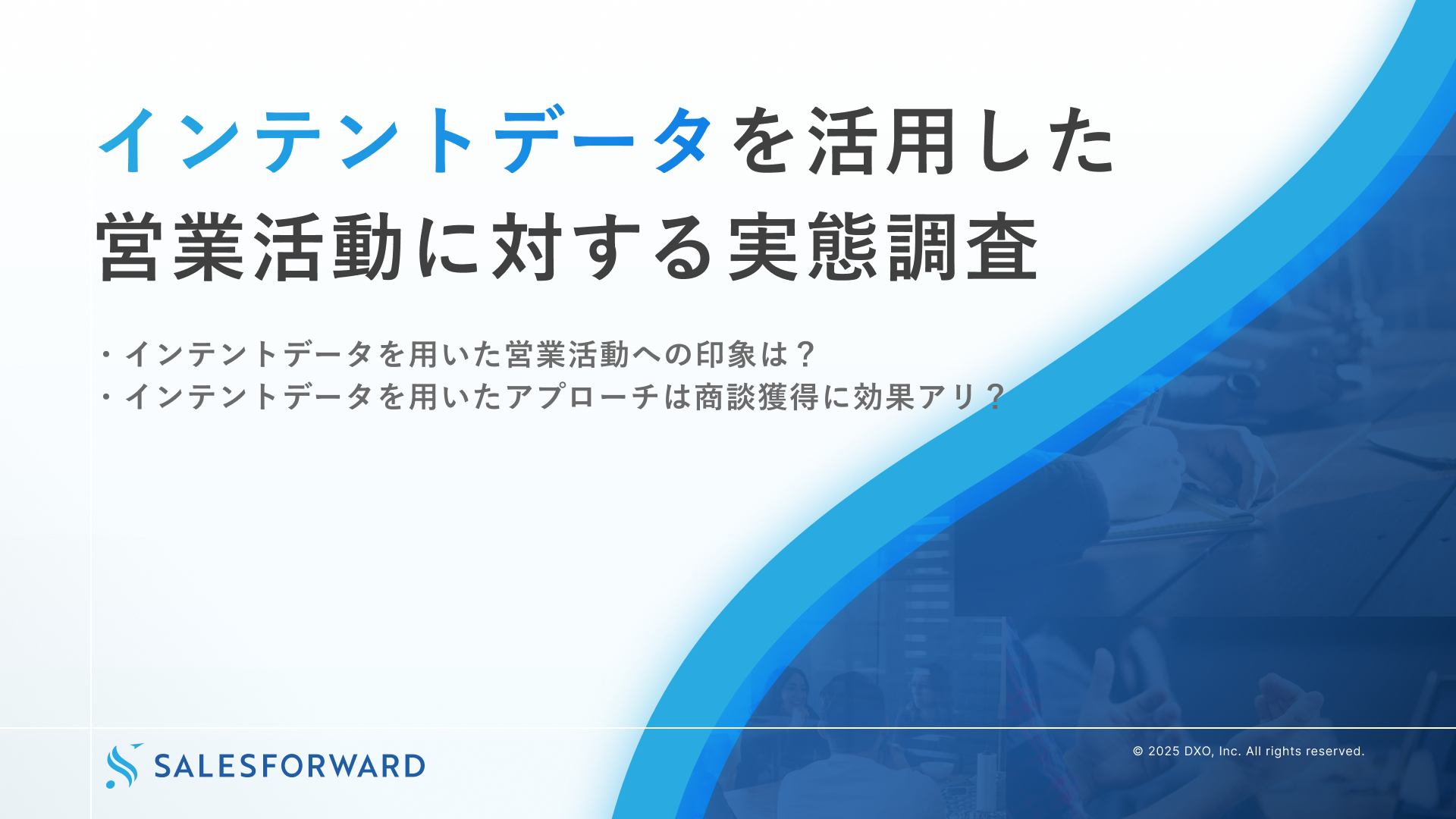リードナーチャリングとは?その定義と効果的な実践方法を解説
2024/11/13

「リードナーチャリングって何だろう?」「リードナーチャリングって何で必要なんだろう」「リードナーチャリングのために何をすればいいのかな?」といった疑問についてお伝えします。ご興味のある方はぜひお読みいただければと思います。
リードナーチャリングとは?
まず、このリードナーチャリングの意味ですが、リード(lead:見込顧客)のナーチャリング(nurturing:育成)で「見込顧客の育成」を指します。
見込顧客といっても、その対象がどれくらい商品やサービスを購入したいと思っているかの度合いは様々だろうと推測がつきますよね。これらの異なる見込顧客に対して、それぞれの購入検討の段階を先に進めていくように促す施策をリードナーチャリングと呼んでいるのです。
リードジェネレーションの違いは?
リードナーチャリングの類語にリードジェネレーション(lead generatioin:見込顧客の獲得)という言葉があります。このリードジェネレーションとリードナーチャリングはどう違うのでしょうか。
順番としては、まずリードジェネレーションが先の段階を指します。例えば展示会などでのターゲットの名刺の取得、自社Webサイトへの問合せ受信、あるいはWeb検索での上位表示を狙ったSEO(検索エンジン最適化)対策などがリードジェネレーションに該当します。
そしてこのリードジェネレーションによって見込顧客となった対象へ、その商品・サービスについての有益情報を提供するなどして商品・サービスの購入検討を促すのがリードナーチャリングというわけです。
リードナーチャリングはなぜ重要?
そもそも、このリードナーチャリングはなぜ重要なのでしょうか。ここではその理由をお伝えします。
顧客の購買プロセスが長期化している
第一に、顧客側の理由として購買プロセスが長期化していることが挙げられます。
伝統的な購買プロセスでは営業がアプローチして情報提供、予算獲得などを経て購買の実現に至ったものですが、現在ではまず顧客がインターネットから情報収集するところから購買プロセスがスタートし、その検討を経て営業にコンタクトするようになっています。また、検討・購入段階でも内部統制強化の影響で予算獲得や実施のための稟議書決裁までの過程が緻密になっています。
このように顧客の購買プロセスが長期化していることから、営業側としてもこれに合わせた顧客の長期的な育成が必要になってきており、リードナーチャリングの重要性が高まっています。
受注確度の高いユーザーにリソースを集中できる
第二に、販売側の理由です。
見込顧客はまだ商品やサービスに対する理解が浅いために営業がアプローチしてもなかなか受注まで至りません。そこで、リードナーチャリングによって顧客の理解を深めてから営業がアプローチするという流れにするのです。
これにより営業は受注確度の高いユーザーへの接触にリソースを集中でき、受注までの生産性が向上します。
リードナーチャリングの基本的な流れ
ここからはリードナーチャリングの基本的な流れを説明します。
リードの獲得と分類
まず、リードジェネレーションによって獲得した見込顧客情報を整理することから始めます。
この見込顧客情報は担当者によって別々に取得、保有されていることに加え、名刺交換や自社ウェブサイトへの問合せ情報など、情報取得時のフォーマット自体もバラバラですのでまずは社内で共有するリストに一元化する必要があります。
そして、名刺交換相手など認知が始まったばかりの見込顧客、問合せなど能動的に情報収集を行っている段階の見込顧客など、検討度の異なるステップごとにその見込顧客を分類します。
アプローチ方法の検討
次に分類した見込顧客ごとにアプローチ方法を検討します。
例えば、「名刺交換相手には定期的なメールマガジンや無料説明会の案内を送付するところから始めよう」「Webサイトからのお問合せにはすぐ電話して話を伺おう」といった具合に対応の検討を進めます。
施策の実行と改善
このようにしてアプローチ施策が決まったら実行、そして改善が重要です。
施策を実行して見込顧客の関心が高まってきたらアポイントメントを取得し、営業担当者に引き継ぎます。
そしてアポイントメント取得率や受注率などのデータを取得すると共に、アプローチ施策がうまくいっているかどうかも確認して改善するというPDCAサイクルを回していくのです。
代表的なリードナーチャリングの手法
続いて、代表的なリードナーチャリングの手法を紹介します。
メール配信(メルマガ)
リードに対してメールを配信します。
月次や週次など定期的なメールマガジンのほか、検討度の段階によって異なる内容のメール、予め設定されたスケジュールに沿って自動的に配信されるステップメールなどの活用が考えられます。
リードナーチャリングでメール配信を活用する場合にはメール開封率や自社サイトへの流入状況などのデータを収集して分析できるとよいでしょう。
コンテンツ配信
ホワイトペーパー(商品やサービスの内容を詳細に記載した資料)やオウンドメディア(企業ブログ)など、商品やサービスの紹介を行うコンテンツを配信します。
メールマガジンにオウンドメディアのリンクを張っておき、さらにオウンドメディアにホワイトペーパーのダウンロードURLを張っておくといった具合です。
広告出稿
リードナーチャリングの手法の一つとしてリターゲティング広告があります。
リターゲティング広告とはインターネット広告の一つで、自社サイトを訪問したことのある人や既に自社広告をクリックしたことのある人に対して、外部サイトで再度自社広告を表示させるというものです。繰り返し広告を閲覧してもらうことで商品やサービスへの理解を深めることを狙います。
一般的な広告はリードジェネレーション施策、認知を狙うものであるのに対して、リターゲティング広告は認知した人に理解を深めてもらうリードナーチャリング施策というわけです。
SNS
スマホの普及によってSNSはBtoCばかりでなく、BtoBでも有効な手法となってきています。
例えば複雑な説明を必要とする場合、より分かりやすい説明をしたい際などは伝達に優れた動画を活用してSNS上で広めていくことが考えられます。またSNSではユーザーとのコミュニケーションが可能なのでロイヤリティの向上が期待できます。
このほかにもフォローコールやセミナー・イベント開催といった方法があります。フォローコールとは見込顧客に対して定期的に電話をして接触を維持することです。購入検討状況の進捗・変化を確認したり、最新情報を提供したり再提案・変更提案を行うことで営業につなげる/失注を防ぐ確率を高めるほか、失注したことを把握するといったことにつなげられます。
またセミナー・イベント開催では見込顧客に対して無料説明会を開催して商品やサービスの理解促進を図ります。セミナーは対面で行うことで参加者としても安心感があり、説明者にとってもプレゼンテーションの手応え、参加者の反応が分かりやすいという特徴が挙げられます。
いずれも見込顧客に直接接触することで相手の反応を感じ取り、プラスアルファの情報を提供できるなど臨機応変な対応をすることも可能になります。また、接触のなくなってしまった見込顧客にDM(ダイレクトメール)を送り、セミナーや展示会に再び招待するというのもリードナーチャリング手法の一つです。
まとめ
この記事ではリードナーチャリングとは何か、リードジェネレーションとの違い、リードナーチャリングの重要性、そして代表的な手法について説明してきました。いかがでしたでしょうか。
これらのことについて理解していただけたのではないかと思います。最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
目次
[ ]
お役立ち資料
検討フェーズ企業を捉える、データ起点の営業事例
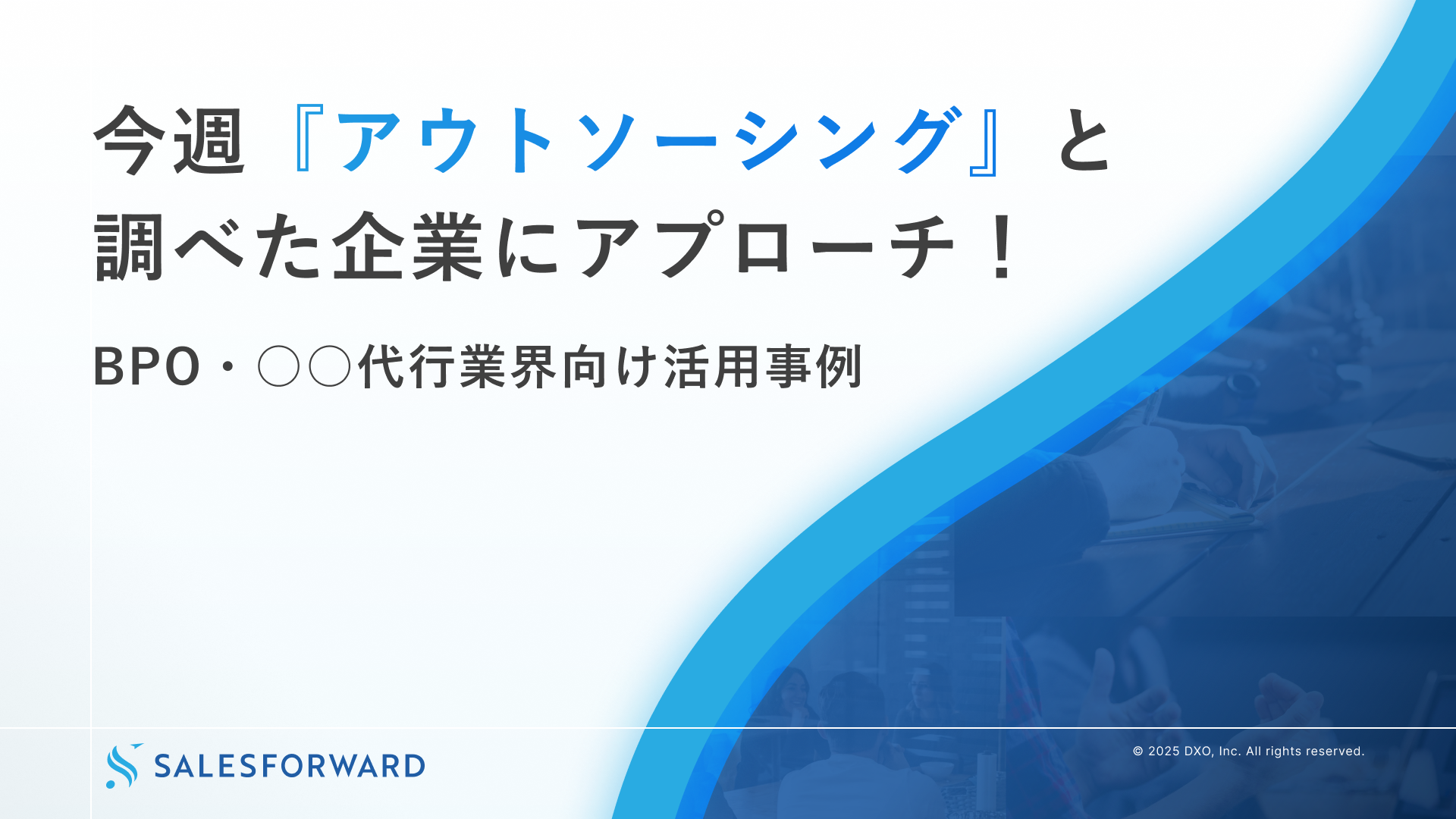
企業がサービスや外注先を調べ始めるタイミングは、営業にとって最も成果につながりやすい瞬間です。 SALESFORWARDでは、検索行動データをもとに、今まさに検討中の企業を可視化し、誰に・いつ・何を提案すべきかを明確にできます。本資料では、BPO・各種代行業界を例に、検討タイミングを逃さない具体的な営業活用シナリオを解説します。
資料請求するお役立ち資料
検討フェーズ企業を捉える、データ起点の営業事例
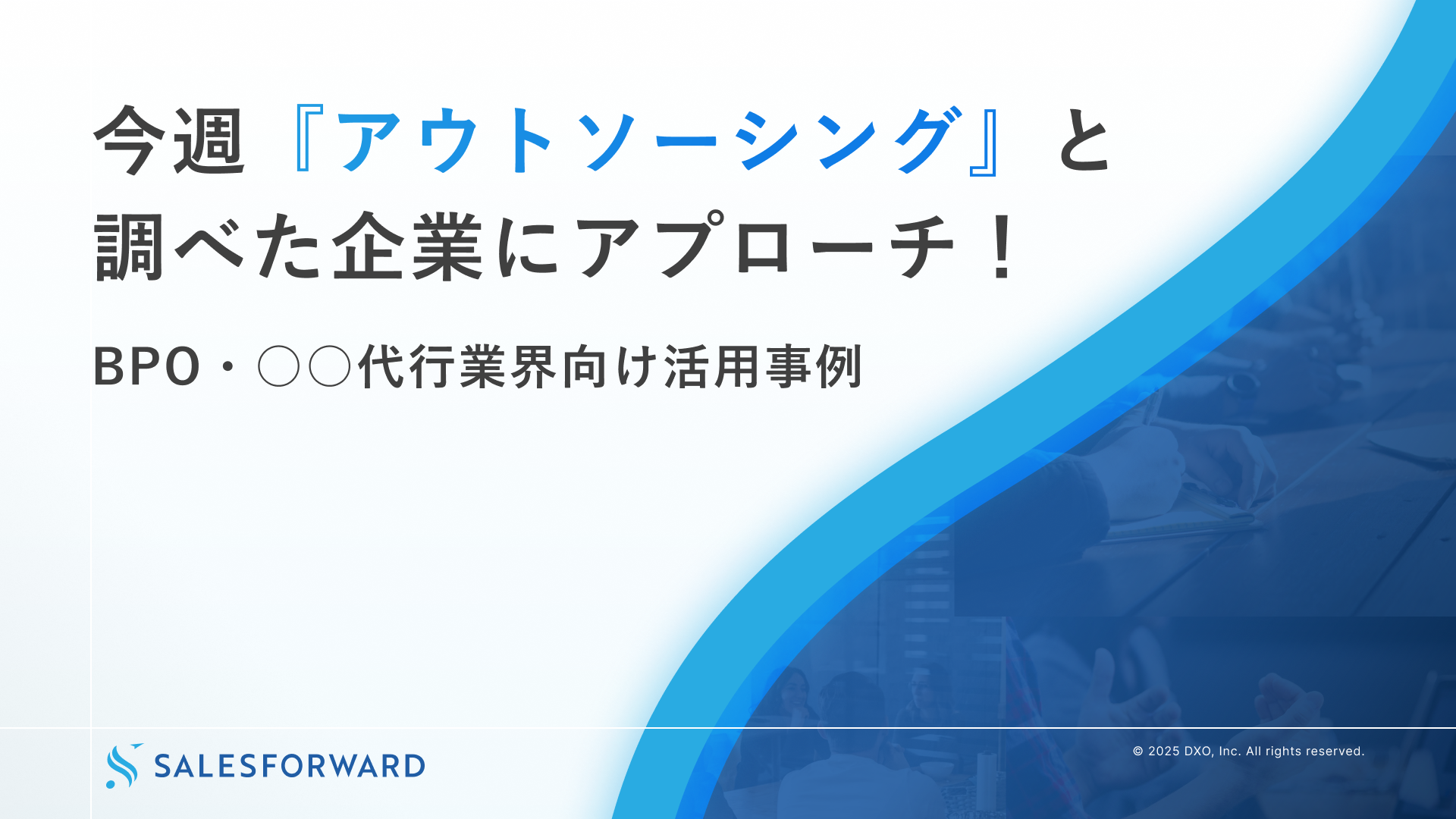
企業がサービスや外注先を調べ始めるタイミングは、営業にとって最も成果につながりやすい瞬間です。 SALESFORWARDでは、検索行動データをもとに、今まさに検討中の企業を可視化し、誰に・いつ・何を提案すべきかを明確にできます。本資料では、BPO・各種代行業界を例に、検討タイミングを逃さない具体的な営業活用シナリオを解説します。
資料請求する関連記事
-

コールドリードとは?ホットリードとの違いと主な獲得手法を解説
マーケティング
2024/12/26
-

フライホイールモデルとは?近年注目されるビジネスモデルとマーケティングにおける活用事例
マーケティング
2024/12/25
-

ダイレクトメール(DM)って今でも有効?デジマ全盛期にあえて紙媒体を使うべき3つの”ワケ”
マーケティング
2024/12/11
-

Facebookのリード獲得広告とは?設定方法や利用する際のポイントを解説
マーケティング
2024/10/22
-

リード獲得広告とは?特徴や配信媒体別の強みをわかりやすく解説
マーケティング
2024/10/21
-

動画マーケティングで期待できる効果とは?代表的な手法ごとに紹介
マーケティング
2024/10/8